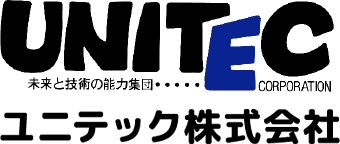Contents
モータのブラシ摩耗が起こる主な原因
最も身近なモータの一つに、「DCブラシ付きモータ」があります。シンプルな構造ということもあり、小学校の理科の実験やおもちゃなどに使われていますので、「モータ」というと、このモータをイメージする方が多いかもしれません。
このモータの最大の特徴は、「ブラシ」と呼ばれる機構です。モータは、コイルと永久磁石との間に働く磁力によって、引きつけ合ったり反発しあったりする現象を利用して回転しています。ブラシはこの現象の一部を担っており、回転運動するための重要な部品です。回転部と常に接触している構造のため、摩耗現象が避けられない部品です。
ただ、その摩耗速度は様々な条件で変動します。今回は、この摩耗現象について詳しくみていきましょう。
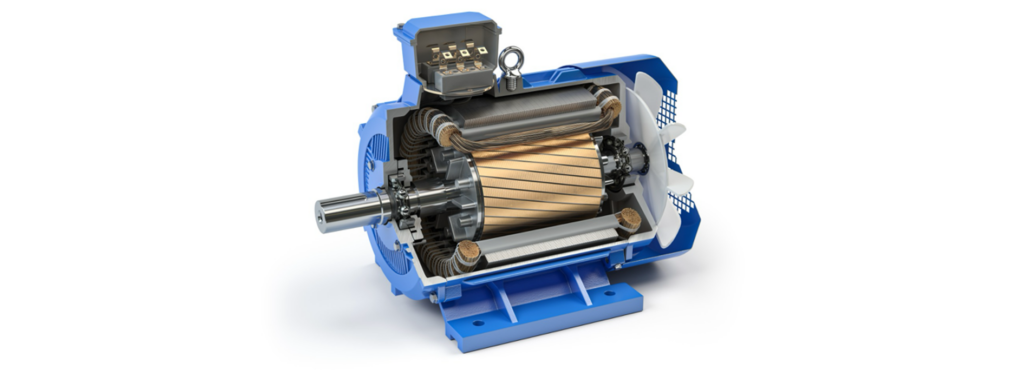
接触圧の不均一
コイルに絶えず電気を流すために、ブラシはコミュテータと呼ばれる部品に常に接触し、電気的接続を保っています。この接触はバネ力によって実現されており、バネがブラシをコミュテータに押し付けるような形で設置されています。(ブラシ自体がバネ性をもった金属で構成されているものもあり、この場合はバネがないように見えますが、原理は同じです)
消しゴムを強く擦るのと同様に、強く押し付ければ、ブラシが早く摩耗します。そのため摩耗の速度をコントロールするためには、適切な接触圧になるよう、モータの部品設計、工程管理などが大切です。コミュテータ表面形状、ブラシの取り付け位置誤差、モータ回転軸の偏心度合いなど、接触圧が変動する要因は細かく見ればたくさんあります。
ブラシの摩耗速度はモータの寿命に直結しますので、モータの個体ごとの接触圧がバラつくと、寿命が個体でバラついてしまいます。寿命品質を保つためには、接触圧に関するあらゆる項目を加味した設計が重要です。
電気的負荷
モータを回すために、ブラシからコミュテータに常に電流が流れています。電流が流れるところは発熱するため、ブラシにも熱が発生します。この熱はブラシの摩耗を促進する要因になります。また、コミュテータにはスリットが入っており、このスリットをブラシが通過し、電流の接続が切り替わる瞬間、アーク放電(火花)が発生します。これも、ブラシ摩耗を加速させます。
電流値が高いほど、発熱・アーク放電の影響は大きくなるため、ブラシ摩耗の観点からは適切な負荷でモータを使用することが重要なポイントとなります。
コミュテータの表面状態
コミュテータの表面には、温度や湿度、電流、ブラシの材質などによって酸化被膜が形成されることがあります。この酸化被膜は、必ずしも悪いものではなく、適量に形成されることで潤滑性が良くなり、摩擦の低減やコミュテータの保護につながります。
しかしこの被膜は薄すぎたり、厚すぎたりするとブラシの摩耗が増えることにつながってしまいます。モータの使用環境下によって被膜状態は変化しやすく、安定した状態にするために様々な添加剤が加えられているブラシ材質もあり、ブラシメーカでは日夜努力が重ねられています。
回転速度の変動
急加速、急停止、急反転などで、回転速度の急激な変動が発生すると、ブラシにどのような影響があるでしょうか。例えば、ダルマ落としを勢いよく弾けば、一段取り除くことができますが、弾かずゆっくり手で押せば全体が移動する、ということはみなさんもおわかりになるかと思います。
ブラシとコミュテータとの間でも、急な速度変化とゆっくりな速度変化とでは、与える影響が変わると考えられます。
回転速度の急変化は、ブラシとコミュテータとの接触状態が急変化することを意味します。ブラシとコミュテータ間の接触が不均一になり、特定の部分が過剰に摩耗するなどといったことが起こり得ます。使用運転条件を考えずモータを選定してしまうと、こういった影響を受けブラシ摩耗に問題が発生することにもなりかねません。そのため、用途を視野に入れたモータ選定が重要であるといえます。
外部環境要因
特別な処理をしていないモータは、振動、水、砂、ホコリなど、外部環境の影響を強く受けます。ブラシ付きモータの中には、外観上ブラシとコミュテータとの接触部に分解することなく外からアクセスできるものもあります。こういったモータの場合、水はもちろん、砂やホコリが侵入すれば、ブラシの摩耗に大きな影響を与えてしまいます。
また、振動の多い環境での使用の場合、ブラシとコミュテータとの接触具合に影響を与えるので、摩耗への影響はもちろん、電気的接続が阻害され、回転動作へ悪影響もあり得ます。
ブラシ摩耗が引き起こす悪影響
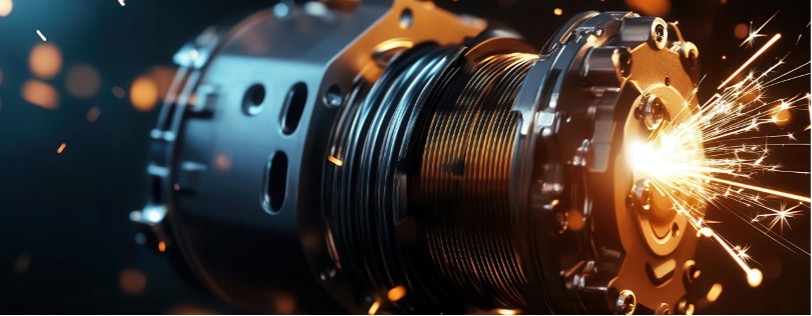
性能低下
ブラシが摩耗すると、コミュテータとの接触面積の変化や、コミュテータのスリット部の目詰まりによる電気的接続障害など、正しい電流の流れが妨げられます。この結果、本来のモータのパワーが発揮できず、回転数やトルクの減少、効率の悪化などが発生します。最悪の場合、ショートやモータの停止などにもつながる可能性もあります。
発熱
摩耗したブラシを使い続けると、ブラシとコミュテーター間でのアーク放電が大きくなり発熱や過電流による加熱などが生じやすくなると考えられます。こうしたことが原因で火災が発生しないとも言い切れません。家庭で使われる掃除機や、電動ドライバなどに使われるモータが、こういった状態に陥ることもあります。
調子が悪くなったモータ製品は使い続けることはせず、修理や買い替えなどを検討するほうが賢明です。(とはいえ、安全装置などが組み込まれている製品も多数ありますので、無理な使い方をしなければ基本的には心配不要です)
騒音・振動
ブラシの摩耗は、騒音や振動の増加にもつながります。摩耗が進行したブラシはコミュテータとの接触が不安定になり、こすれる音や異音、接触不安定からくる振動などが発生することがあります。モータの回転が不安定になることにもつながり、さらなる振動発生、さらなる摩耗などを引き起こし、故障につながる恐れがあります。
ブラシ摩耗を予防する方法
適切なブラシ材質の選定
材質の選定はやはり基本になります。回転数、負荷、振動など、モータの用途を考慮して最適な材料の選定が大切です。
コミュテータの表面仕上げ
定期的なメンテナンスでコミュテータの状態を確認することが有効です。表面が荒れていたり、黒い被膜で覆われていたりした場合は、研磨機などで磨いたり、部品交換などを行うことが有効です。
接触圧の調整
バネ自体の設計定数確認はもちろんのこと、設置時の寸法、適正荷重が発揮できているかという設計上の確認と、取り付け位置誤差管理など組み立て工程時の確認も大切です。接触圧に大きなバラつきが発生しないかの確認が重要です。
運転条件の改善
急加速・急停止・急反転をしないなど、モータの使い方に注意するだけでも改善が見込めます。ブラシ付きモータの性質をよく理解すれば、どのような使用方法が一番適切であるかということが自然に見えてくるはずです。ブラシ付きモータに限らず、各々のモータの特徴を理解することで、最適な運転条件を設定でき、本来の力を引き出した使い方が可能となります。
外部環境の管理
屋内で使用することで粉塵を排除、振動が発生しないシステムへの組み込み、温度変化の少ない環境に置くことで結露などを避けるなど、ブラシとコミュテータの接触を阻害する要因の排除が有効です。
無ブラシモーター(ブラシレスモーター)への移行
根本的な解決策として、ブラシがないブラシレスモータへの移行が可能であれば、ブラシ摩耗に関する問題は完全に解決します。ブラシ付きモータの最大のメリットは電源につなぐだけで回転が可能、というところにあります。この点を重視した用途の場合、ドライバが必須であるブラシレスモータへの移行が難しい場合が多いと思います。
しかし、もし移行が可能であれば、寿命を何十倍に伸ばすことも条件によっては可能ですので、メリットは大きいといえます。
モーターのブラシ摩耗でお困りの方はユニテックへご相談ください
弊社は長年のブラシ付きモータの設計経験がございます。必ずお役に立てることがあると思いますので、ぜひお気軽にご相談ください。