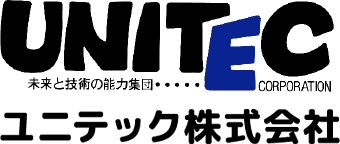Contents
モータの騒音・振動が生じた時はまず原因を特定する
「回転運動」を生み出すモータは、原理的に多かれ少なかれ、騒音・振動が必ず発生します。
これは物理的に避けられない現象です。ただ、その程度は状況によってさまざまであり、時にそれが許容できない場合もあります。振動・騒音をいかに小さく抑えるかということは、モータ開発時に注力するポイントの一つです。
しかしながら、通常であれば起きるはずがない騒音・振動が、不具合として検出されることがあります。この場合は、まずその原因を特定することが重要です。原因に対してさまざまなアプローチを行い、対策を打っていきます。

モータの騒音・振動が生じる原因の種類と対策方法
機械的要因
具体的な不具合の内容
①軸受の嵌め合い不良
軸と軸受の嵌め合い値が不適切であったり、環境温度による部品の膨張収縮によって嵌め合いが変化したりすることで、軸の回転にガタが発生することがあります。
②軸受の電蝕(金属製ボールベアリングの場合)
金属製ボールベアリングに電圧が蓄積され、内部のボールに錆が生じることがあります。滑らかな回転が求められるボールには、非常に高い寸法精度が必要とされており、多少の錆が発生するだけで回転が阻害され、騒音につながることがあります。
③ローターのバランスの不均衡
ローターが安定して回転するためには、動バランスと静バランスという評価値を調整する工程が必要です。このバランスの概念は、「洗濯機の脱水工程」を想像するとわかりやすいかと思います。脱水開始時は、ガタガタとうるさく振動しているのが、回転速度が上がったり下がったりを繰り返しながら、次第にガタガタ音が収まり、スムーズに高速で回転していく様子を観察したことがある方もいると思います。
これは、ガタガタと音を立てながら回転するうち、内部の洗濯物が偏りなく均等に配置されていき、バランスが取れた状態となると、安定して高速で回転ができる、といったことが起きています。「洗濯物」と言う名の「錘」が、均等に配置された状態ともいえるでしょう。
ローターのバランスが不均衡という状態は、まさにこの洗濯物が偏った状態と同じです。この状態では、振動が大きくなってしまうことがわかると思います。
④連結部の緩み
ネジやスナップフィットなどで、固定されるべき箇所が緩んでいると、回転から発生する微細な振動が、緩み部で増幅され悪影響を発生することがあります。
⑤機械的共振
物体には必ず固有振動数というものがあります。回転から発生する振動数が固有振動数と一致してしまうと、共振現象が発生し、大きな振動となって現れることがあります。
共振現象は、弱い地震が大きな建築物を容易に崩壊させる、といったことも起こします。条件が一致してしまうと大きな問題になることがあります。
原因を特定する方法
①軸受の嵌め合い不良
・モータの軸を手で回し、ガタの有無を確認する
・軸の外径・軸受の内径の寸法を測定する
②軸受の電蝕(金属製ボールベアリングの場合)
・ボールベアリングを分解調査(分解時にダメージを与えてしまうことを避けるため、ベアリングメーカに依頼)
・使用環境を調査し、軸受に電圧が発生する環境であるかどうかの調査(モータを改造し、ベアリングに電極を接続。その状態でシステムにマウントさせ、電圧を測定)
③ローターのバランスの不均衡
・モータ駆動時の振動を測定(振動のピーク周波数と回転数の関係性を調査)
・ローターのバランス値の測定
④連結部の緩み
・顕微鏡などで連結部の状態を確認し、緩みの形跡、破損、摩耗、亀裂などを観察
・ネジの緩みトルクの測定
⑤機械的共振
・ハンマリング試験にて固有振動数を調査し、モータ駆動時に発生する振動周波数との関係を調査
対策方法
①軸受の嵌め合い不良
・設計寸法の見直し
・ベアリング内径と回転軸を接着する
②軸受の電蝕(金属製ボールベアリングの場合)
・ベアリングに電圧がかからない用、使用環境を変更・金属→セラミックボールベアリングに変更し、電蝕が起き得ない状態とする
③ローターのバランスの不均衡
・バランシングマシンにてローターのバランス調整を実施(小さな錘をローターにつけ、バランスを調整する工程を実施)
・出荷検査にてモータ駆動時の振動を測定管理
④連結部の緩み
・トルクレンチでの締め付けトルク管理を行う
・ネジ用接着剤の使用
・組立治具を使い、スナップフィット部の確実な嵌め込みを行う
⑤機械的共振
・ハンマリング試験の結果を元に、使用条件を事前に顧客と調整。
電気的要因
具体的な不具合の内容
①電源の不安定
電源の供給能力が不足すると、モータの回転が不安定になり、回転速度が早くなったり遅くなったりといった状態になることがあります。これにより、回転音が大きくなったり小さくなったりを繰り返すことで、騒音・振動の不具合につながることがあります。
②電磁的干渉
モータは、内部で電流・磁界の大小の変化を起こし続けることにより、電磁波を発生します。この電磁波が周囲の環境に影響を与えることがあります。
③不均等な電流分布
何らかの要因により、コイル各相の抵抗値が一定にならないor想定より大幅に異なる抵抗値になった場合、相ごとに流れる電流が不均等な状態となることがあります。その結果、回転挙動が不安定となり、振動・騒音となって現れます。
原因を特定する方法
①電源の不安定
・検査機の電源システムと顧客で使用している電源システムのスペック確認・比較
・さまざまな電源を使ってモータ駆動時の電流波形や特性を比較(回転数、電流値など)
②電磁的干渉
・モータから発せられる電磁波の測定
・電磁波測定環境と顧客でのモータ使用環境を比較
・モータが使用される顧客装置システムの理解
③不均等な電流分布
・電流波形の測定
・コイルの各相の抵抗値を測定
・レアショート試験の実施
・ピンポール試験の実施(破壊試験のため、やるかどうかは状況による)
対策方法
①電源の不安定
・モータの能力を十分に発揮できる電源を使用する
・顧客との事前のすり合わせ
②電磁的干渉
・モータ部品選定
・駆動回路のチューニング
・外部環境の調整
③不均等な電流分布
・巻線仕様の設定
・巻線工程・検査方法の管理
構造的要因
具体的な不具合の内容
①モータの設置不良
顧客装置にモータを取り付ける際、その取り付け方や、使い方により、さまざまな影響が生じることが考えられます。例えば、下記のようなことが想定されます。
・4箇所のネジ止めを想定したモータを2箇所のみで固定している
→不安定な設置が、機械的なビビリ音などの発生につながる
・回転軸にかかる負荷が設計想定よりも高い
→ベアリング等の損傷につながる
・モータ同士が接触する位置で使用する
→互いに振動が影響し合い、騒音発生やモータ外装の摩耗につながる
②フレームの共振
モータ単体の共振は、「機械的要因」でも述べました。ここでいう共振は、顧客装置側との共振です。顧客装置の固有振動数とモータの振動が共振してしまう可能性もあります。
③複数の振動源の影響
モータのような、振動源となり得るものが複数搭載されるシステムの場合、各振動源の駆動条件の中で、一部の組み合わせにおいて問題が起きる、といったことも起き得ます。
原因を特定する方法
①モータの設置不良
実際にモータがどのように設置されるかを現地確認し、不適切な状態がないかどうかチェック
②フレームの共振
・フレームの振動の程度を実測調査、振動の大小を調査(振動測定ピックアップを多数取り付け等にて実施)
・フレームの固有振動数を調査し、モータの駆動条件との関連を調べる
③複数の振動源の影響
②と同様の調査を、より広い範囲、複数モータの複数駆動条件を組み合わせて実施する
対策方法
①②③とも対策の方向性は同じで、下記の2つとなります。
①振動源からの振動の伝搬を少なくする
具体例:モータとフレームとの間に防振ゴムを挟む
モータの回転数を低くし、振動の振幅を小さくする(音圧も小さくなる)
②共振をさせない
具体例:モータの駆動回転数を変更して、フレームの固有振動数と一致しないポイントで使用する
フレーム部品の素材や構造を変更して、固有振動数をずらす また、ギヤドモータの振動が原因となる場合は、ギヤ内グリス充填量を増やす、静音グリスを採用するなどの方法も効果的です。
環境要因
具体的な不具合の内容
①温度・湿度変化
モータには保管・使用において、対応温度・湿度範囲が指定されています。これを外れた環境での使用は不具合の原因となります。
また、急激な環境温度の変化はモータ内部結露に繋がり、カーボンブラシに悪影響をきたす、ベアリング内ボールに錆が生じるなど、騒音発生につながります。
②水・塵・埃の侵入
防水・防塵仕様のモータではない場合、屋外等で使用すると水・塵・埃が内部に侵入する場合があります。これはさまざまな回転を妨げる要因につながり、不具合を引き起こします。
③腐食ガスなど、特殊環境による部品腐食
腐食ガスが発生する環境は、モータの運転にさまざまな悪影響を及ぼします。コイルの絶縁コーティングを溶かしてしまったり、ブラシ部の摩耗を早めてしまったり、複数箇所の錆の発生、電子部品の腐食などなど……振動・騒音につながるだけでなく、さまざまな故障につながります。
原因を特定する方法
環境要因による不具合モードはさまざまな種類があり、原因特定は難しいです。不具合現物の状態を社内だけでなく外部機関に依頼して、詳しく調査することがまず重要。それだけでなく、顧客に協力をお願いすることが必須です。モータの使用環境に関して、5W1Hをよくヒアリングすること、現地に出向いて状況を観察すること、顧客の担当者だけでなく、現地の作業者や、エンドユーザにも協力を仰ぎ、「再現試験」を行うことが大切になります。
対策方法
原因がわかれば、方向性は下記の2つとなります。
①モータに問題が起きない環境で使用してもらう(使用環境を変えてもらう)
②環境に耐えられるモータに変更する(モータを新規で専用設計する)
ここでの注意として、モータを専用設計する場合。生産数量がある程度多くない場合、コストはどうしても高くなってしまいます。
モータの騒音・振動が発生した際の対応手順

不具合の診断
詳細な診断を行い、不具合の根本原因を特定することが必要となります。
顧客での不具合発生品の場合は、まず不具合品に対し出荷検査と同じ評価を行い、基本的な特性をチェックします。さらに、顧客で起きた不具合が再現できるかどうかをチェックします。再現できない場合、顧客でのフレームなどへの取り付け状態を確認する必要があるため、分解する前に顧客との相談をまず行います。
再現が確認できた場合、分解調査を行います。ブラシ付きモータの場合、ブラシの状態・コンミテータの状態・ベアリングの状態調査実施、ブラシレスモータはほぼ非接点のため、ベアリング状態調査を行う、ギヤドモータはギヤボックス内歯車の歯面検証、グリス状態調査等を行ったうえで診断します。
影響評価
不具合の原因や詳細が明確になったら、生産ラインや他のシステムに与える影響を評価します。その不具合は……
- 今回のみの特別な例で、今後同様のことが起きる可能性は限りなく低い現象
- 継続的に発生し得るが、その確率は高くはない現象
- 潜在的に生産品全てに発生し得る現象
どういう特徴の不具合であるのかを見極め、対策としてどのような選択肢を選ぶのかを検討します。
選択肢の評価
上記の影響評価を考慮して、以下の各選択肢のメリットとデメリットを比較します。
- 使用環境を変える
- 生産工程を見直す
- モータを修理する
- モータを交換する
- モータ構造を一部変更する
- モータ駆動プログラムを一部変更する
- モータをイチから開発し直す など
最適な選択肢の選定
コスト、時間、信頼性、安全性、ダウンタイム、在庫処理、顧客への影響などを総合的に考慮して最適な解決策を選定します。基本的には、その選択が上流であればあるほど、変更の難易度は高くなります。
例えば、不具合品が仮にトルクに余裕がある製品だった場合。モータ(ー)の運転電流を絞ることで振動の振れ幅を抑えることができ、音圧も下げられるので、この場合は顧客の使用環境の変更orモータ駆動プログラム一部変更するのみで済みます。
しかし、共振周波数をずらすことや振動成分を下げる試みが必要な場合、開発をイチからやり直すレベルでの変更が必要です。トライ&エラーを繰り返す膨大な時間・費用が必要となります。
モータの騒音・振動でお困りならユニテックへお任せください
ユニテックなら、お客様の利用用途に合わせた最適なモータを設計・製造可能です。騒音・振動を抑えたいというご希望がありましたら、カスタムモータ開発・製造を得意とするユニテックへぜひご相談ください。